みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)
先日の記事でもお知らせしました通り、今年度の年末調整が終了いたしまして、本日無事!還付まで完了いたしました(‘ω’)ノ
サクッと源泉徴収票の配布準備を行い、会計処理までやってしまいましたので、今日はその仕訳処理の仕方と、お給料明細への表示について書きたいと思います(*’ω’*)
源泉所得税を還付するときの仕訳処理
みなさんご存じの通り、源泉所得税は預り金でございます。
毎月、大体の額(ちゃんと決まった額だけど・・)を預かり、年末に多すぎた分を還付、足りない分を徴収するという仕組みですね!
預かった時の処理ですが、スタンダードな(?)仕訳は
→ 普通預金 / 預り金 1,000円
となります。預かったのち、この預り金(源泉所得税)は税務署に納めますので、納めた際には
→ 預り金 / 普通預金 1,000円
という仕訳が起きます。そうしますと、預り金の残高はゼロ円、普通預金も預かる前の残高に戻ります(*’ω’*)
これを12か月繰り返した後、還付の処理を行います。
今回の還付が3,500円だったとしますと、
→ 預り金 / 普通預金 3,500円
という仕訳になります。ここで、預り金の帳簿残高はマイナスの3,500円になってしまいます(‘ω’)ノ
上の例で見てみますと、「1年間通じて12,000円の源泉所得税を納めたけれども、年末調整の計算をした結果、8,500円になった!ので、納めすぎた3,500円を返そう(還付)!」ということになります。この場合の還付とは、税務署に納めた税金が、従業員さんに還付になる、ということです。
本当ならば、税務署から直接還付になれば分かり易いのですが、ここは仕組みがちょっとややこしく、会社から還付になります。
ですので、一度会社は「税務署に代わって、従業員さんに還付」を行います。
源泉所得税は、会社で一度預かりましたが、既に税務署に納めてしまっており「預り金」としては持ち合わせていません。ですので、還付をした結果、マイナス残高になってもここはOKとなります(`・ω・´)
上の例ですと、3,500円のマイナス残高になっているはずです。
この後、翌月以降の源泉所得税を預かる上で、預り金のマイナス残高は解消されていきますので、ここは慌てなくても大丈夫ですよ(*’ω’*)
年末調整以降の、源泉所得税の納付処理の仕方や納付書の書き方については、また次回の記事を参考になさってくださいね(*’ω’*)
お給料明細での、年末調整還付金の表示
年末調整のあった月の、お給料明細はすこーし複雑ですね(´・ω・`)
普段ですと、お給料明細は大きく分けると「支給項目」と「控除項目」に分かれており、源泉所得税は「控除項目」の「所得税欄」に記載されています。
年末調整のあった月は、
①源泉所得税を預かる
ということと、
②源泉所得税を還付する
という二つの事柄が重なります。
ですので、「預かる処理」と「還付する処理」を一つの「所得税欄」に表示するなると、預かり額から還付額を差し引いた金額を記載することになります。
上の例を見ますと、12月は1,000円を預かって、3,500円を還付する、ということになります。
ですので、1,000円-3,500円=2,500円となって、差し引き2,500円を還付します。
このとき、「所得税欄」は、控除項目になっています。
控除項目の場合は、「お給料から引く額を、そのまま書いている」ので、「お給料に足す金額は、マイナスで書く」必要があります。
今回の例では、「所得税欄」は「△2,500円」と表示されることになります。
なかには、お給料明細の欄に「年末調整額」等として、還付の金額を別個に記載できるようにしてあるものもあると思います。
こちらは分かり易いですね(*’ω’*)!
「所得税欄」には、そのまま12月に預かる金額を。「年末調整額」には、還付する金額をマイナスで書き込めばOKとなります。
ちなみに、還付を期待していても、不幸にも(?)徴収になる場合も時にはありますね(;_;)
この時は、普段、源泉所得税を徴収するときと同じように仕訳を行います。お給料の明細には、12月の源泉所得税の徴収額と合わせて書いてしまうか、「年末調整額」等に別箇に記載して徴収します。
まとめ
以上、簡単に「還付をする時の仕訳処理」と、「お給料明細への記載の仕方」を見てきましたが、参考になりましたでしょうか。
仕訳に使われる勘定科目は、実際のところは会社によって異なる場合もあります。「預り金」を使わずに、「未払金」勘定を使ったり、「仮受金」を使ったり・・等々です。
年に1度しかない処理ですので、忘れてしまいがちですが、年末調整の流れを確認して、間違えない様に仕訳をしていきましょう(`・ω・´)
関連記事
『毎月ゼロ納付が続く場合は、納期の特例もアリかも。6か月に1度で手間が省ける!』
『年末調整の後はゼロ納付で!ゼロ納付の考え方と、納付書の書き方&仕訳かた』

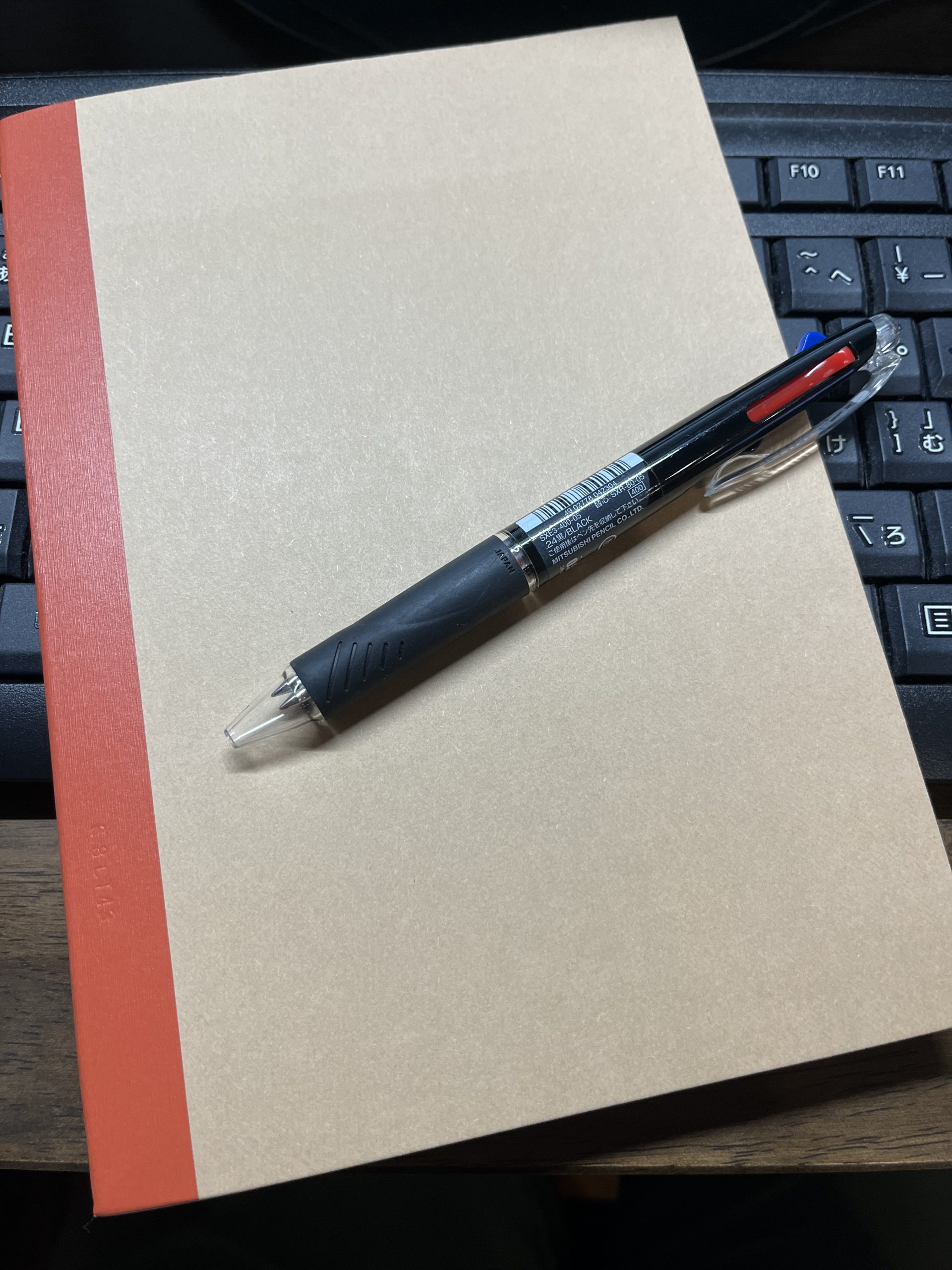




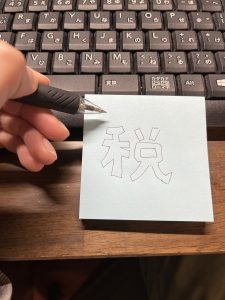
コメント