「そろそろ、会社の福利厚生も考えないと・・。」
「社員の定着が悪いのは、もしかして福利厚生がイマイチなせい!?」
「まって!そもそも福利厚生と法定福利費って何が違うの!?」
などなど、福利厚生にお悩みではありませんか???
実は、長年会社に勤めていても「えっ、これって福利厚生の一環だったんだ!」と知らずにいたり、また他の会社を見て「えー!そんな福利厚生あるの!?いいな~!」というのがあったり、実は福利厚生ってたくさんあって、いざ

よし!とりいれよう!
と思っても、どれからやったら良いのか迷うと思います。
今回は、大企業のように社員食堂までは作れなくても、何かないかな~と探している中小企業の社長さんや総務さん向けの記事になっております。
会計事務所勤務で、数々の会社さんを実際に見てきた経験から、「人気があった!」サービスの他、「意外と不評であった!」というモノもご紹介しますので、是非ご参考になさってくださいね(^_^)
そもそも・・福利厚生費と、法定福利費の違いは??
どちらもとてもよく似た勘定科目で、誰しも一度は
「一体何が・・どう違うの!?」
と迷ったことがあるかと思います。
一言で言ってしまうと、「法定福利費」は、法律でやりなさいと言われている福利費。
ということになります。
たとえば、法定福利費の例は
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災
- 子ども・子育て拠出金
といったモノです。毎月のお給料から法定で控除しているものですね。
一方で、福利厚生費となりますと、コチラはとても幅が広くなります。
今回ご紹介してゆくのは、この「福利厚生費」。
大企業の様に、大々的に食堂を作ったり、年間に何百万と費用はかけずとも、中小企業であっても工夫次第で他社と違った福利厚生に取り組む事ができると思います。各々の企業にあった福利厚生があるかと思いますので、じっくりと検討してみてください!
社内の整備も福利厚生になる
社内の整備、と言いますと・・



給湯室を作る!あと、冷蔵庫を置く!
などと、具体的にモノを設置するイメージが強いかもしれません。
もちろん、コレらも福利厚生の一環です!従業員の立場からしますと、落ち着いてお昼休憩を取れるスペースや冷蔵庫、ポットや電子レンジなんかがそろっていると、とてもありがたいモノです。中小企業ですと、そこまで手が回らない場合もありますが、この辺をキチンとそろえてありますと、来客があった際にも慌てずに済みます。
実は、これら細々とした設備を揃えることの他、社内の整備として良く見かけるのは
- 家賃等の補助
- 健康診断に人間ドックをつける
- 従業員の慶弔費の規定を作る
- 短時間の勤務時間を取り入れ、介護や育児をしやすくする
- 育休制度の充実
- 託児・保育施設を設置する
- 資格取得の支援を行う
- 各種休暇を取り入れる
- 確定拠出年金や、財形貯蓄などの財産形成の支援をする
などなど、様々あります。
これらは、大企業などでなくても、予算と相談しながら適宜取り入れることができます。もうすでに取り組まれているものもあるかもしれません。
しかしながら、これらの整備については、例えば社長が
「よし!明日からわが社は・・フレックスタイムだ~!」
と宣言すれば取り入れられるかというと、実は・・違います。
このフレックスタイム(会社で働くコア時間を決める)の様に、取り入れるためには会社の「就業規則や規定」に記載し、場合によっては就業規則を労働基準監督署へ届け出なければならないものもあります。
少し厄介に感じるかもしれませんが、この辺は社労士さんが専門分野となります。賃金規定や就業規則などの見直しとともに福利厚生の整備をしてゆくのもよいかもしれません。
私が実際に見てきた中で、割と好評だったものを二つご紹介します。
資格取得の支援
これは、外部で行っている講座等に従業員を参加させ、資格を取得させるものです。
資格の内容は、事業に関係のあるものにはなりますが、資格自体は従業員個人に帰属します。たとえ、資格取得後に退職してしまっても、資格自体は取り消しになりませんので、同業への再就職であったり、独立であったりと、従業員の助けになります。
「給与は消えてなくなるけど、資格は残るからね!」
と聞いたのを「なるほど~!」と思って聞いていました。会社としては、資格を取ってもらって戦力として長く働いてもらいたいですし、従業員からしても自分の力となるので魅力的です。
各種休暇を取り入れる
休暇というと、一般的にお正月休みやゴールデンウィークなどのほか、介護や育児に際してとれる休暇が頭に浮かびますが、この他に会社が独自に考えた休暇なども設定できます。厳密にいいますと・・
特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入の見られる慶弔休暇や夏季休暇も、企業により任意に設定された特別休暇です。
厚生労働省 特別休暇制度導入事例集2020
ちょっと難しいですね!任意で設定できる休暇!ということです(^_^)
私も従業員の立場から「ありがたかったな~!」と思うのは、「試験休暇」というものです。
会計事務所勤務時代、税理士試験にチャレンジしていた事があります。税理士試験は、会計事務所の仕事に直結する資格試験なわけですが、この試験当日や前日などに休暇を取ることができました。
有給を使わずとも、当たり前のように休暇の申請をすることができ、とてもありがたかった記憶があります(試験は落ちていましたが・・)。
職種や事業によって、独特な休暇がたくさん考えられます。ここで会社の個性を出してゆくのも良いでしょう。
厚生労働省では、特別休暇制度の導入事例集も出しているので、実際の事例をチェックしてみたい方は是非ご覧ください!
参考 特別な休暇制度導入事例/働き方・休み方改善ポータルサイト
外部サービスを福利厚生として利用
福利厚生代行サービス
「福利厚生代行サービス」というのを聞いたことがあるでしょうか。
従業員が増えてきますと、やはり人によって「ほしい福利厚生」はずいぶん変わってきます。会社が独自に各種サービスを探してきて従業員に提供するとなると、やはり大変なモノも出てきます。
そこで、福利厚生を専門に扱っている会社にまるっとお願いする事もできます。
基本的には、会社では従業員さん一人当たり数百円程度で会費を支払い、利用するサービスは従業員さん個人が直接申込みをして利用するパターンになります(サービスの提供会社によって違う場合もあります)。
私の家族もかつて、このパターンで福利厚生を利用していましたが、公共交通機関の利用料金や、映画等の娯楽施設、スポーツセンターの利用回数券が安く入手できたりと、個人の需要に合わせて利用ができますし、毎回「何を使おうか~!」と、従業員本人だけではなく家族の楽しみの一つでもありました。
大手さんですと、(株)リロクラブやベネフィットステーションさんなど有名どころかと思いますが、もっと公共的なものもあります。
お近くのサービスセンターを直接検索するときはコチラの一覧から調べられる様です。
参考 サービスセンター一覧/全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
大抵、勤務地周辺の施設が多く登録してあると思いますので、中小企業の場合はコチラの方が身近に使えるのかもしれません。
一方、実際に私がお伺いしたお客さんの中で、人気があると思いきや・・人気が出なかったモノと、理由もご紹介します。
会社近場の娯楽施設等
実は、人気がなかったモノは会社近場のスポーツジムでした。
私が会計事務所勤務時代に担当していた企業さんで、デスクワークが主なところがありました。ずっと座っての作業なので、さぞやスポーツジムは人気があるだろうと思っていたのですが、担当さん曰く・・
「仕事が終わってまで、同僚と顔を合わせたくない。」
「運動するのは良いんだけど、あまり運動してるところを知ってる人に見てもらいなくない。」
という意見が多かった様です。
なかなかの田舎町でして、この会社の周囲のスポーツジムと言うと、当時は一カ所のみ。仕事が終わって、みんな同じ場所に行きますと、せっかくスポーツジムに行ったのにメンツが変わらずにあんまりリフレッシュできない・・という理由の様でした。
ですので、スポーツジムが悪いという訳ではなく、「利用できる施設が1カ所のみ」というところが敗因かなと思いました。
もちろん、
「毎日、お風呂に入って帰っています!」
という強者(?)もいたと聞いていますので、個々も従業員さん個人の感覚によるところも大きいかと思います。
ちょっとユニークで取り入れやすい外部サービスは?
ここまで見ていただくと、



ん~!結局何にすれば良いんだ!?
となるかもしれません。それはその通り、何人も従業員さんがいると、万人に受けるモノを探すのは至難の業です。
また、経営者と従業員では見ているモノも世界も違うので、なかなか何を求められているのかお互いに分からないものも多いです。
役立つ!と思って頑張って規定を整備した割には、社員的にはすぐ利用できるサービスの方が求められていたり・・
ですので、取り入れる際にはアンケートや聞き取り調査を行ってみたり、お試しに期間限定で取り入れて見たり・・ということで反応を見るのも良いかと思います。
ちょっと変わったサービスもご紹介しますので、気になった方はお試ししてみてくださね!
株式会社KOMPEITO
朝の情報番組でも紹介されたようなのですが、冷蔵庫を設置しておいて、従業員は商品を1個100円~で購入できるモノです。
なかなかお昼時間に外に出られない場合でも、配達員さんが冷蔵庫の中身を補給しておいてくれるので、いつでも利用ができます。
株式会社オンリースタイル
個人的にめちゃくちゃ気になるのですが、オフィスにバナナが届くというオフィスバナナ専門店という新しい世界です。

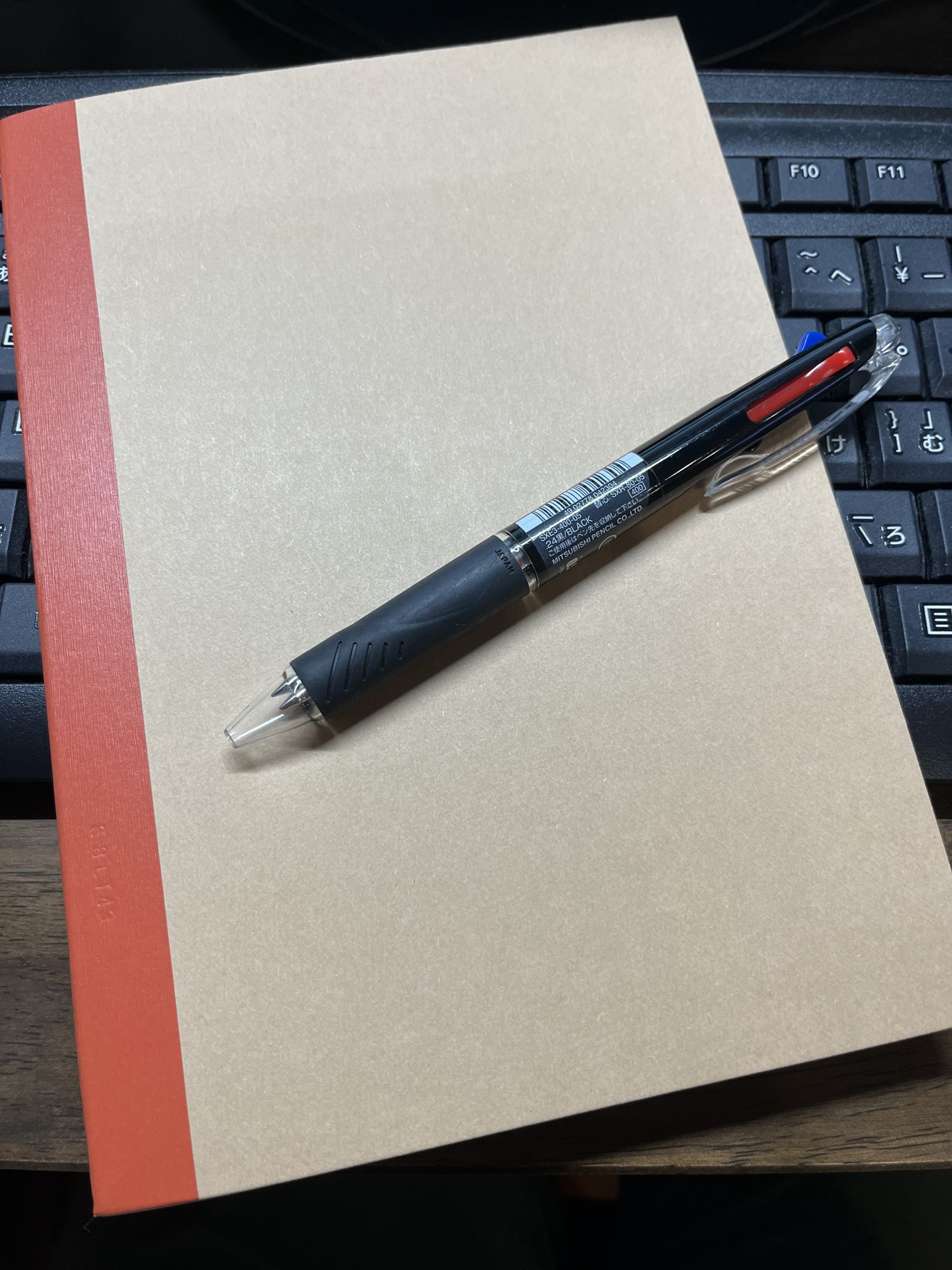




コメント