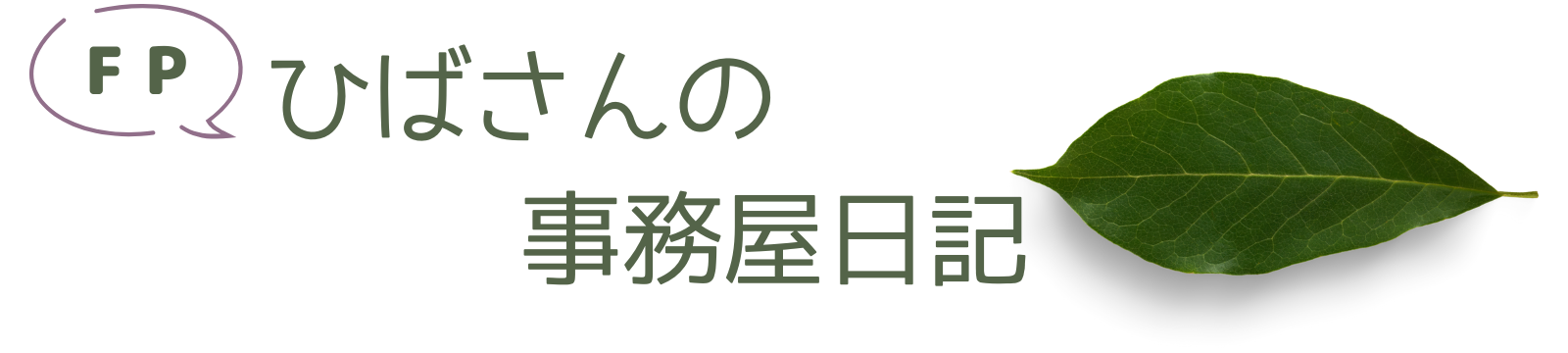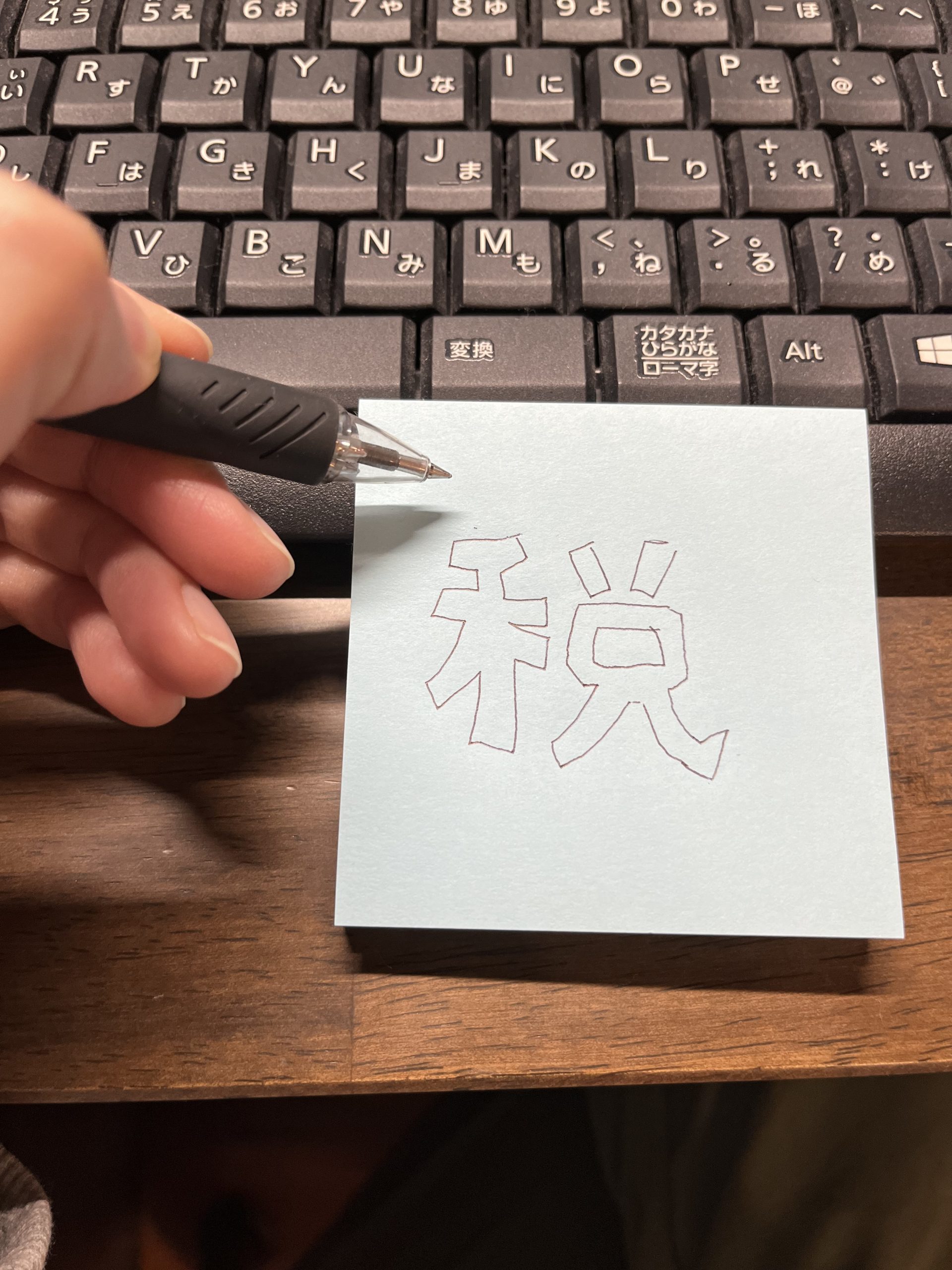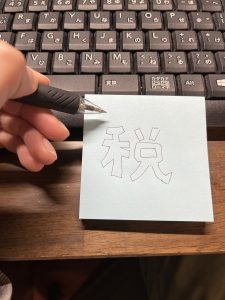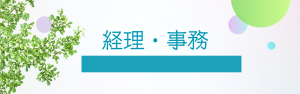先日、ハンドメイド作家さんの場合のインボイス対応について記事をご紹介しましたが、

よかった・・!自分はやらなくていいな!!
と思う方もいらっしゃれば、



え、ええ~・・でも、ホントに大丈夫かな(;゚ロ゚)??
とまだまだ不安に思っている方。さらに



自分はガッツリ対象じゃ!!
という方まで様々かもしれません。。
今回は、残念ながら(?)インボイス対象となった方でも、2023年の税制改正で負担軽減措置ができたそうなので、一体誰が対象になって、何がどうなるのかをザックリと確認してみたいと思います。
参考 「インボイス、対応しなきゃダメ??ハンドメイドの場合について考えて見ました。」
こんな人は負担軽減対象に!
前回記事「インボイス、対応しなきゃダメ??ハンドメイドの場合について考えて見ました。」では、インボイス制度について「業種によっては、インボイス(適格請求書等)に対応しなくても大丈夫!」という内容をご紹介しました。業種によっては、うっかり「みんなやってるから・・!」と慌てて登録してしまうと、払わなくても良い消費税等を納税することになってしまいます。
今回は、「自分はしっかりとインボイス発行事業者に登録しなきゃならない」という事業者等のうち、一定の方はインボイスの導入にあたって事務等の負担軽減が受けられるよ!という内容のものです。
では、実際にどんな方が対象になるかということですが・・
①インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった人
②一定規模以下の事業者(中小企業)
です!
それぞれ、納税額の計算がしやすくなったり税額が軽減されるほか、少額取引については帳簿保存のみで税額控除が受けられるという内容です。
他にも、少額の値引きに対するモノや、登録制度の見直しなどもありますが、大きなところは上の2点かと思います。
慌てて損してしまわないよう、軽減できるモノは無いか、ちゃんとチェックしていきましょう!
次からはそれぞれ、対象者とその内容を見ていきますよ(^_^)
参考 財務省「令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について」
インボイス制度対応のため、免税事業者から課税事業者になった場合は納税額が売上の2割で計算できる。
「インボイス」という言葉が出てくるまでは、ずーっと消費税申告は無用であった事業者さん・・つまり、免税事業者だったけれど、インボイスに対応するために課税事業者となった人が対象です。
きちんと言うと、基準期間(2年前)の課税売上が1,000万以下等である事業者さんが対象で、消費税の納税額を計算するにあたって「売上税額の2割」を納税額とすることができる制度です。
これは、令和5年10/1~令和8年9/30を含む事業年度が対象で、個人事業主の場合は令和5年10月~12月の申告から令和8年度分の申告までが対象です。
実際、この制度を使わない場合、消費税の計算は「実額計算(本則課税)」もしくは「簡易課税」という方式で計算を行います。
本則計算の場合は、売上の他、仕入や一般管理費の税額もきっちり計算しますので、とてもめんどくさいです。
簡易課税は、本則計算に比べて計算はしやすいですが、業種によってはこの特例を使った方が税額が低く計算できる場合が結構あると思いますので、この制度を使わない手はありません。
では、何か届け出が必要なのかと言うと、事前の届け出は不要、申告時に適用するかどうかを選択するのみで良い様です。
とはいえ、売上・収入は税率ごとに把握しておくことは必須となりますので、まずは売上の管理はしっかりとしていきましょう!
具体例を一つご紹介しますと、
売上170万(内、税額70万)経費150万(内、税額15万)のサービス業であった場合
本則計算をしたときの消費税納税額 → 70万ー15万=55万
簡易課税で計算したときの消費税納税額 → 70万ー35万=35万 *簡易課税の時は、みなし仕入率の税額を引きます
売上の2割で税額計算したときの消費税納税額 → 70万×2割=14万
となり、売上2割で計算するのが一番低く納税額が抑えられます。
また、本則計算の場合は、上の式でサクッと引いている「15万」も、いちいち計算して出さなければならないので何度も言いますが面倒です。
手間を見ても、納税額を見ても売上2割は助かります。
中小事業者の少額取引はインボイス不要
これは、「2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方」が対象となります。
法人であれば2期前、個人であれば2年前の課税売上が1億以下であれば対象。
または、法人であれば前期、個人であれば去年の上半期の課税売上が5千万以下の方が対象ということです。
対象となった場合、1万円未満の課税仕入については、帳簿の保存のみで税額控除ができますという制度です。
インボイス制度では、インボイス等の保存をすることで仕入税額控除をすることができるようになる訳ですが、1回の仕入が1万未満であれば、帳簿のみで税額控除ができるということです。
消費税計算をする上で、「本則課税」や「簡易課税」、また今回「売上の2割」で計算する方法があると上でご紹介しましたが、「本則計算」をする場合は、「仕入税額」を計算する必要があります。この時、仕入にかかる請求書や領収書等について「インボイスに対応したモノを保存しておく」必要が出てくるわけですが、この場合に「1万未満」は帳簿のみでOK!!ということなのですね。
ですので、消費税計算を「簡易課税」でやっている場合や、「売上2割」で計算する場合はあまり恩恵は無いかもしれません。が、取引先が本則計算をしている場合は保存も必要になってくる可能性はありますので、覚えておいた方が良いかもしれません。
対象となる期間は令和5年10月1日~令和11年9月30日の間です。
補助が受けられるものは何?
ここで、補助が受けられるモノについてもみていきます。今回は、次の二つです。
- 小規模事業者持続か補助金
- IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)
ここまで読んでいただくと分かるように、インボイスに対応するためにはそれなりの時間と労力と・・集中力と・・そして、対応するためのソフト等にかかるお金も必要になるのがわかるかと思います。
このため、いくらか補助に対しても改正があったようです。
一つ目は、小規模事業者持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されるというものです。
補助の対象となるモノは、税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等などです。が、「補助」ということで、対象者すべてがもらえる訳ではないので(審査があり、評価の高い順に採択されます)、100%当てにしてはいけない様ですね。
とはいえ、小規模事業者にとってはインボイスに対応するための経費もバカになりませんので、自社が対象になるかどうかは1度チェックしておいたほうが良いでしょう。
詳しくチェックしておきたい場合は、コチラのサイトがわかりやすいかと思います。
参考 「全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金 一般型 ガイドブック 第7版/2023.3.3」
もう一つは、IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。



インボイス対応と言っても・・やっすいソフト入れただけだし(^_^;
という場合でも、もうちょっとチェックしておいた方が良いかもしれません。
補助の加減が撤廃されたことで、少額からの補助も可能(とはいえ、申請にかかる労力を考えるといかがなモノか・・。)ですし、パソコンやタブレットなどのハードから会計ソフトや受発注ソフトも対象です。
言われてみると・・「あ、あれも対象か!?」なんてものもあるかもしれません。
こちらのサイトではシュミレーションができる様になっている様ですので、すでに対応してお金が出て行っている方はコチラで確認してみると良いかも。
まとめ
今回は、「すでにインボイスは対応しなきゃ・・」という方向けに、「負担軽減になる改正があったよ!」というお知らせでしたが、いかがだったでしょうか。
2023年改正で出てきたと言うことは、それだけ周囲から「めんどい!」「嫌!」という声があったからかな!?などと勘ぐってしまいますが、すでにインボイスは決定事項であるので後はいかに負担を最小限に抑えるかというポイントで乗り切っていくしか無いのかと思います。。
補助金などは、作成する書類なども多くてちょっとまためんどくさいんですけど・・、もらえるモノはもらい、取り組めるモノはどんどん取り組んで見てくださいね(^_^)
*補助金対応の他、インボイスそのものの対応なども相談する場合は、税理士が良いと思います。お探しの方はコチラもどうぞ!