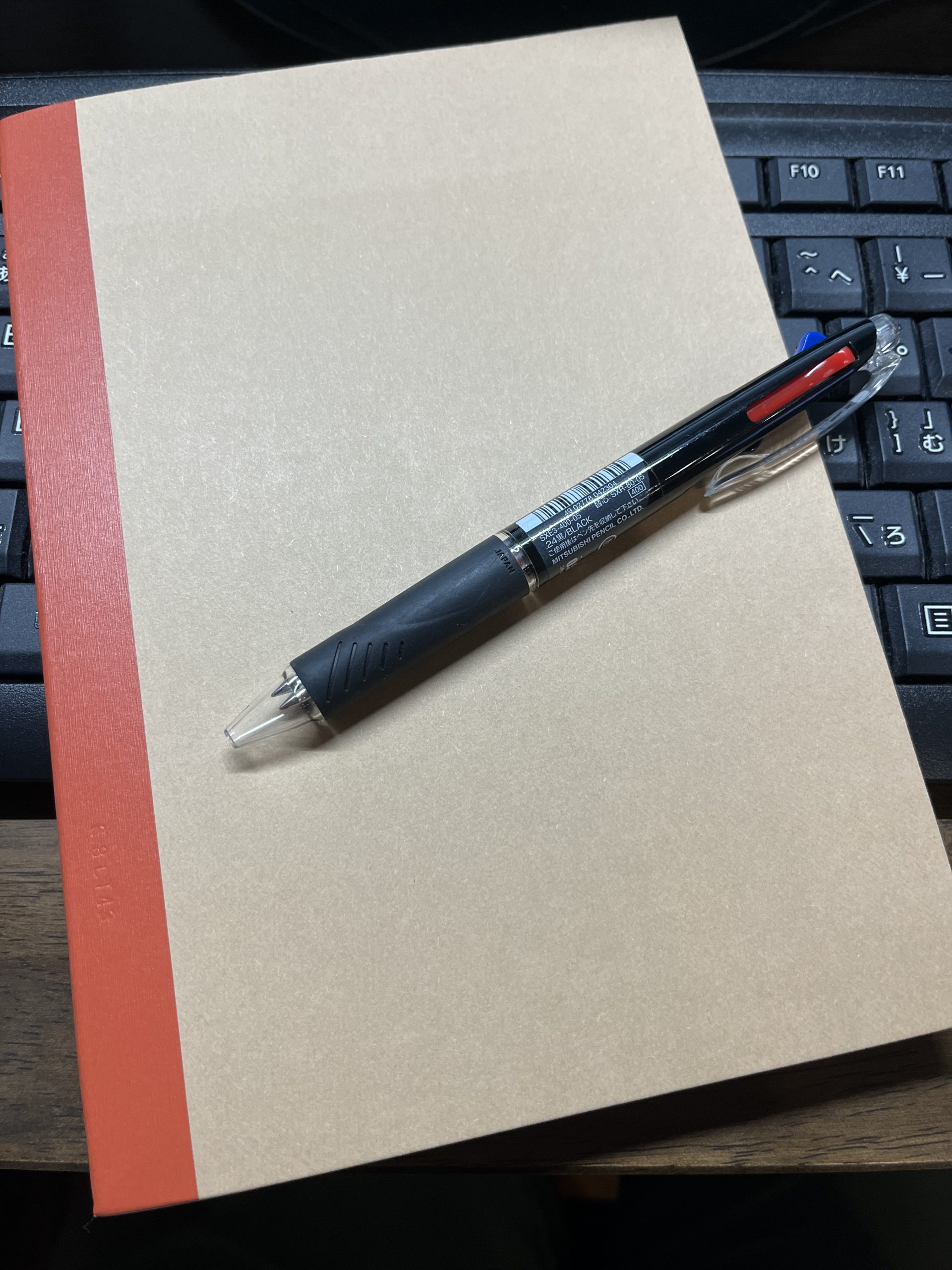みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
今日は、朝から納品書をメモ用紙にすべく、適したサイズにカット、カット、カットする作業の連続です。
最初に言ってしまいますと・・
納品書は7年保存しなければなりません。

カットしてメモ用紙にしてるじゃん!?
全世界に向けて、保存期間を無視したことを告白してしまいました・・。これは失言か・・あとから後悔するかな・・
でも・・内容としては、請求書とかと全く同じだし・・
納品書としての役割は既に終えていると思って・・ですね!
結果、今回は100万の札束三つくらいのメモ用紙が出来上がりました。そんなにメモすることもないけど、電話メモとかに活用しましょう。そんなに電話も取らないけど・・
しかし、この納品書、みなさんどう処理していますか?
今日は、納品書についてちょっと考えてみることにします。



果たして、納品書はいるのか!?いらないのか!?
そして、いったい何年持っていればいいのか。
請求書や領収書との違いは??
なんて点も見てみますよ!
まずは「納品書」って何ですか?
仕入をしたときや、備品を購入した時、または何かのサービスを受けた時(たとえば、会社のパソコンが動かなくなって、ソフト屋さんに診てもらった時など)にもらう、
『〇月✕日 コピー用紙(A4版 上質紙白 100枚入り) 5セット △△円』 納品しました。
などと書かれた書類のことですね。
これ、実をいうと・・法的には発行する義務はありません。
では、なんで発行するのかと言えば、ひとえに
『商品、サービスの提供があったと証明するため』
なんですね。
この納品書を渡すとともに、『確かに受け取りました。』という『受領書』や『受領印』を貰ったり、『納品書控え』を貰ったりします(名称は多々)。
つまるところ、
『確かに納品しました!』
ということと、
『確かに受け取りました!』
ということの証明になるわけです。
お金を持ってお店にお買い物にいく場合は、その場で決済が済んでしまう場合がほとんどかと思いますので、特に「納めた、納めていない」という事は問題にならないかと思います。
が、問題になるのは『掛売り』をしている場合です。
この場合、例えば『1か月分の仕入代金、翌月末にまとめて支払います!』という契約をしている場合などですが、翌月に発行された請求書を見て
「え、この〇日の商品、うち受け取ったかな??」
「いやいやいや、納めたでしょ!」
というトラブルが起きないとも言い切れません。
こういうトラブルを防ぐためにも、納品書は出した方がいいね!という事なのです。
納品書を確認すれば、いつ納めて、また誰に渡したかを確認することができます。
「納品書」は、「納品した!」「受け取りました!」という証明のための書類。
保存期間は7年間
保存期間については、会社法だとか、法人税法だとか、消費税法なんかの法律がイロイロ各自
「5年!」
とか
「7年!」
とか
「10年!!」
などと主張していて
「結局何年なの!!?」
と声高に叫びたい気持ちになります。が、とりあえずは法人税法で定められている7年と思っておいて良いでしょう。
7年です(結論)。
この・・大量の納品書を7年・・。
内容は請求書と同じ・・これを7年・・。何度も言いますが、7年・・。
先に、納品書の役目は「確かに商品・サービスの受け渡しがあったという証明することである」と書きましたが、考えてもみてください。
もう7年も前に納品したものについて、
「これ、たしかに納品したよね?」
なんてケース・・
ないでしょうから、ぶっちゃけ7年も必要ないんじゃないの??と思うのですが(個人的に)、おそらくは税務調査が行われた際に7年くらい昔のを調べる必要が出た際に廃棄しているとまずいのでしょうね・・



あいや・・廃棄しちゃったよ・・(記事冒頭のメモ用紙づくり)
現在では多くの会社が取引に際して、納品書を発行しています。ひばさんの勤め先でもそうですし、取引会社さんでもほとんどのところで納品書を発行されています。
発行したら7年の保存義務です。
どうせ発行するなら、ちゃんと活用できる書類がいいですね!
「納品書」は発行義務はなし!ただし、発行したら保存期間はある。
多分ダメな納品書はこういうこと・・
先に書いた様に、納品書は
「商品・サービスの受け渡しが確かにありました!」
と証明する書類です。
それも、ただ発行するだけでなく「受け取りました」というサインなりハンコなりで、「誰が受け取ったのかも分かる」様になっています。
が、なんと月末にまとめて納品書が送付になるパターンもあるかと思います。
え・・、見たことないですか?それは優秀です!
ひばさんが今感じております、『こんな納品書、意味ないよね!』というのはですね、
『商品と同時に手元に届かない納品書』
です。
ひばさんの勤め先にも何件かあるのですが、月に何十件と仕入れした分の納品書が、半月、もしくは一か月分をまとめて送付されます。
納品された際は、出荷伝票というものがついてきまして、この伝票と納品物との突合せを行います。
お気づきでしょうか・・。
この時点で、納品書はそのお役目を「出荷伝票」に奪われております!
この「出荷伝票」によって、納品された商品や個数などはチェックできます。ですので、後でまとめて送られてきた納品書によって、改めて商品のチェックすることはありません。すでに売れてしまっている場合も多いですので、納品チェックとかの段階では既にないのです。
ここまで読んでいただくと、



なんだ!いらなくね!?納品書!
と思われるかもしれませんが・・
やはり、先ほどから書いております様に、納品書は「商品やサービスの提供があった証拠」になります。
また、納品場所が社外であるなど、納品場所まで確認に行けない時などは、納品書を受け取ることで「あ、届いたな~。」という事がわかります。
ですので、ぜひ「納品書は納品時の発行」を心がけて、納品書がそのお役目をバッチリ果たせるようにしてあげてくださいね!
納品書と請求書、領収書などとの違いは。
ところで・・納品書の他にも、取引に際してはいろんな書類が出てきます。
一般的には、「見積書」から始まり、売り上げた後「納品書」が発行され、「請求書」を出すことで入金され、「領収書」を発行します。
いずれも、お客さんとの取引上、提供するサービスの内容だったり、数量や金額などのすり合わせや確認上、大切な書類になってくるかと思います。
「納品書」が「商品・サービスの提供があった証拠」であるのに対し、「請求書」は取引先に対して「納品書の通りに提供した商品・サービスに対しての金銭の請求」をする書類であり、「領収書」はその「対価を受け取ったよ!」という証拠書類になります。
ですので、記載内容は一見して同じであっても、それぞれ別な意味を持った書類になります。
ちなみに、納品書は特に発行について法的義務はありませんが、領収書は「請求されたら出さなきゃダメ」っとなっています。(民法486条)←Wikibooks
そして、この領収書ですが、受け取り金額が5万円以上の場合は印紙が必要になります。以前は3万以上のモノが印紙の対象でしたが、現在(令和5年2月2日時点)では領収金額が5万以上のものが要印紙ですので、お気を付けくださいね~。
まとめ
ここまで、納品書について「捨てちゃダメなのか。保存はどのくらいしないとだめなのか。請求書などとの違いは何なのか。」などを見てきましたが、いかがだったでしょうか。
納品書とは「商品・サービスの受け渡しの証拠」であるということ。
「納品した・してない」のトラブルを避けるためのものでもあるという事。
なので、納品時に出さないと意味が無いよっという事と、
発行する法的義務はないけれど、発行されていれば7年は保存しないといけないよ!ということも見てきました。
請求書や領収書と比べると、いささか重要度が低そうな納品書ですが、保存期間は7年と長期になります。
折角発行するのですから、形だけの発行ではなく、取引先さんにおいても重宝されるような納品書発行をしてみてくださいね!
おまけ。2024.1月からは電子帳簿保存法が・・
2024.1月から、電子帳簿保存法が始まりましたね・・!インボイスに並んで事業者の頭を悩ませる出来事の一つ・・。
これは、2024年1月1日以降に発生する電子取引は、必ず電子データのまま保存しなければならない!というものですが、みなさん対応はできていますでしょうか。。
めんどくさい手続きではありますが、今回の増え続ける納品書を考えると「あれ?スキャナー保存しとけば意外とらくちんなんじゃないか・・!?」という感じも。。そう、初めからデータにしておけば、「場所がないから廃棄しなきゃ・・いや、でも保存期間が・・」などとモヤモヤしなくても良いはず。
もし会計ソフトでやよいをお使いの方であれば、「スマート証票管理」を検討してみてください。やよいユーザーであれば無料で使えますし(あんしんサポートに加入する必要あり)、インボイス制度にも対応していますので、あれこれ悩まなくても済みます。
「製品サポート」のページから「スマート証憑管理を使い始めたい」という項目に進むと、利用開始の流れを確認できます。
やよいのクラウドサービス(無料体験プランを含む)を契約している+デスクトップソフトのあんしん保守サポート(無料導入サポートを含む)に加入している
方で、まだ利用していないよ~!という方は、ぜひチェックしてみてください!⇩⇩⇩